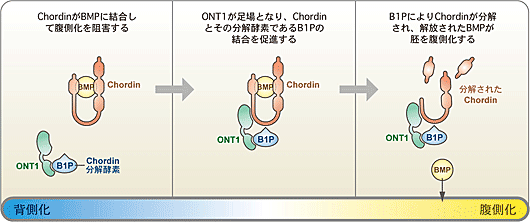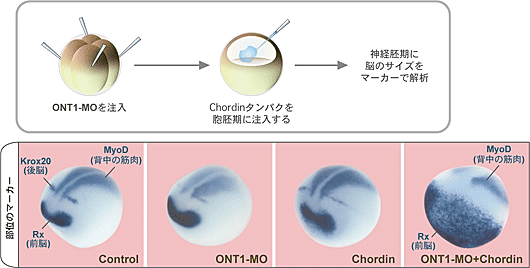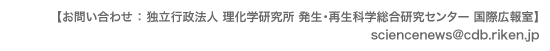| 正しい脳のサイズを決定する -神経誘導因子Chordinの分解を制御するONT1の機能- |
|
 |
| |

脊椎動物の胚発生過程では、一つの受精卵が分裂を繰り返す事により、多様な細胞・組織(細胞の機能的な集合構造)を形成する。また、脊椎動物の胚は発生時期が同じであれば、各器官やその前駆組織のサイズは、個体間でほぼ一定であることが知られている。このような、サイズを制御するメカニズムは頑強性を有することが知られている。例えば、アフリカツメガエルの頭部発生はシュペーマン形成体から分泌されるChordinなどの神経誘導因子により誘導される。しかし、シュペーマン形成体を除去、あるいは追加移植しても、最終的には野生型と同等の頭部組織を形成することが以前から知られてきた。このように発生を制御する条件が大きく変動しても、最終的に発生する組織が一定になるメカニズム(発生の頑強性:ロバストネス)は明らかにされていなかった。今回、猪股秀彦研究員(細胞分化・器官発生研究グループ、笹井芳樹グループディレクター)らは、分泌タンパク質ONT1が頭部発生の頑強性に関わる分子であることを明らかにした。この研究成果はCell誌に9月5日に掲載された。
これまで研究グループは、アフリカツメガエルの発生過程において、頭部組織の形成はシュペーマン形成体から分泌されるChordinが胚を背側化することにより誘導される事を明らかにしてきた。腹側からは主にBMP(Bone Morphogenesis Protein)が分泌しており胚を腹側化するが、ChordinはこのBMPに直接結合してその機能を拮抗し背側化させる。このような、BMPとChordinの濃度勾配が胚の背腹軸の決定に関わっている。しかし、ChordinとBMPが互いに拮抗するだけでは安定した背腹軸を誘導することは出来ない。胚は発生過程中に外部からいろいろな外乱にさらされ、発生の制御に関わる分子も条件が変動するからである。つまり安定した発生を実現するためには、例え胚が外乱にさらされても、ChordinやBMPの濃度を一定に保つ機構が必要となる。今回猪股研究員らは、ONT1がChordinの分解を促進する因子として働き、Chordinのタンパク量を適切な濃度に保つ働きがあることを明らかにした。
研究グループでは既にONT1を始め類似の構造を持つ分子群をクローニングしていたが、明確な分子メカニズムは分かっていなかった。そこで、モルフォリノアンチセンスオリゴ(MO)用いたONT1の機能阻害実験を行ったところ、アフリカツメガエルにおいて背側化が促進され、ONT1が背腹軸の決定に関わる分子であることがわかった。更に、ONT1はChordinとOLF(Olfactomedin domain)を介して、またChordinの分解酵素であるB1P(BMP1とXlr)とCC(Coiled-coil domain)を介して結合していることを明らかにした。これらの結果をもとに、研究グループはONT1がChordinとその分解酵素であるB1Pを繋ぐ足場タンパク質(Scaffoldタンパク質)として機能し、B1PによるChordinの切断を促進しているのではないかと考えた。この仮説を証明するために、in vitroおよびin vivoの実験系を用いて検討し、ONT1が足場タンパク質として機能することを明らかにした。つまり、ONT1はB1PによるChordinの切断を促進し、腹側化を促すpro-BMP因子(BMP signalを増強する分子)として機能する。
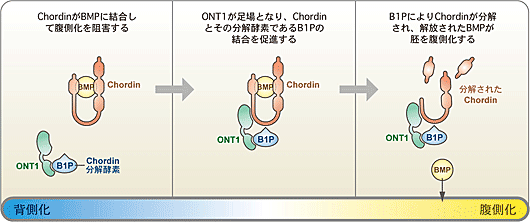 |
|
図1 ONT1はB1PとChordinの足場タンパク質として機能する
|
しかし、ONT1は主に背側領域(シュペーマン形成体)で発現しており、かつ胚を背側化させるとONT1の発現量が有意に上昇する。これは、背側に存在するONT1がpro-BMP因子(腹側化因子)として機能することを意味し、発生学的には矛盾している。そこで、研究グループはONT1が背側領域で負のフィードバックとして働き、Chordinのタンパク量を一定に保つ働きがあるのではないかと考えた。アフリカツメガエルのシュペーマン形成体は摂動に対して頑強性を示す事が知られており、微量のChordinタンパク質を胞胚期の胞胚腔にインジェクションしても大きな表現系を示さないことが知られている。そこで、このような頑強性がONT1によって制御されているのではないかと考え、ONT1のMOを用いてONT1の機能を阻害させた後にChordinタンパク質をインジェクションした。コントロールにおいては、従来の報告通りChordinタンパク質による大きな変化は認められなかったが、ONT1の機能を抑制した胚においては、Choridinタンパク質の注入により胚の大部分が頭部になった。このことから、ONT1は背側に存在する腹側化因子として負のフィードバック制御に関与し、発生の頑強性に不可欠な因子であることを明らかにした。さらに、研究グループはONT1以外にBMPの一種であるBMP2が、すでに報告されているADMP(anti-dorsalizing morphogenetic protein:BMPの一種)と同様に背側領域で負のフィードバックとして機能し、直接BMPシグナルを増強し胚を腹側化することを見いだした。
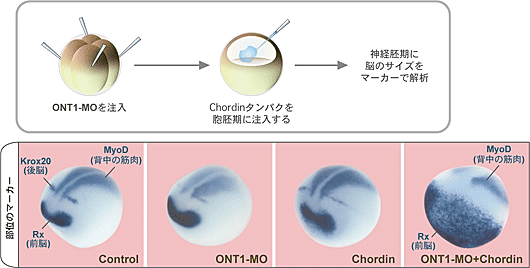 |
図2 ONT1は頭部発生の頑強性に必須な遺伝子である |
このように、ONT1(Chordinのタンパク量を制御する)やADMP/BMP2(直接BMPの量を制御する)のように異なる制御レベルでの二重の負のフィードバックシステムを構築することにより、適切なサイズの頭部形成が可能になると考えられる。おそらく、幾重にも張り巡らされたフィードバックシステムが、発生の適切な組織・サイズの形成を保証し、発生の再現性を生み出すのであろう。猪股研究員は、「今までの発生生物学は決定論的な現象を明らかにしてきました。しかし発生が外乱・揺らぎなどにより危機的状況に陥ったときに、胚はどのようにして正しい発生を回復するかはあまりわかっていませんでした。胚の発生には危機管理マニュアルが存在し、そのおかげで再現性よく発生する(頑強性)ことが可能であると思います。」と語る。この研究は発生過程を適切に行うために生命が持つ複雑な機構の一つを明らかにしたという点で非常に意義のある成果であるといえる。
さらにこの成果を発展させ、iPS細胞や、ES細胞などの幹細胞から「正しいサイズ」の組織・器官を誘導し移植治療などへの応用にも貢献出来ると期待される。
|
| Copyright (C) CENTER FOR DEVELOPMENTAL BIOLOGY All rights reserved. |
|